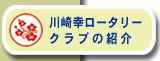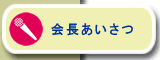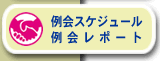| この世にミステリーというものがあるとしたら、私にとって最大のミステリーとは、私自身のこの人生ではないかと思います。私が住まう月心寺は、京都市と滋賀県大津市を隔てる逢坂山にあります。ここに暮らして四十余年。いつの頃からか、私のつくる精進料理を食べたいとおっしゃる方があちこちから訪ねてこられるようになり、月心寺の名は一般にも少し知られるようになりました。
午前一時、町も眠りについたころ、私は仕事にとりかかります。夜明け前にお勤めを始めるのは僧侶の常ですが、私が賭いうちから起き出すのは、鐘を撞くためでもお経を読むためでもなく、料理の仕込みを始めるためです。自慢にもならないことをはっきり申しあげますが(
何事につけはっきりものを言いすぎるのが、よくも悪くも私という人間です)月心寺に来てからこのかた、いっぺんも朝の勤行というものをしたことがありません。
衆生本来仏なり。白隠禅師さまはそう説破されました。
仏像に向かってお経をあげるためではなく、生きたみ仏、すなわち、今日ここを訪れるお客さまに食べていただく蓮根を、ごぼうを、にんじんを炊くために、そしてごま豆腐を最高の状態に仕上げるために、私は早起きするのです。ごまを一時間ほどかけて摺りながらお経を唱える癖がありますが、それはお経を読み終えるのにかかる時間と、ごまがちょうどよい加減に摺れるまでの時間がぴったり合っているからにすぎず、お経はありがたく、読めば功徳があり、だからこのごまもおいしく摺れるなどとは夢にも思っていません。
日本に伝わるお経はお釈迦さまのお言葉そのものではなく、何人もの手を経て中国語に翻訳されたもの。その一言一句を間違わずに読むのが尊いか、今日の出会いのために精魂こめて野菜を炊くのが尊いか。迷わず後者をとるのが私の生き方で、料理は「君がため」につくるからこそおいしくできると信じているので、つくりおきをしたことは一度もなく、生きた仏さまのためには一切の手抜きもありません。私が嫌うのは、しきたりではなく、しきたりに縛られる心なのです。あなたの本分はいったい何ですか、と問われれば、「料理はアマで尼が本職」とへたな酒落で返しながら、私がここでこうしていることの不思議を密かに噛み締めます。
尼僧のくせに料理屋まがいのことをして、ちゃっかリプロなみの金までとって―― と眉を顰める方のあることも知っています。言いたい人には言わせておけ。と思わないこともありませんが、本当のところ、「指摘ごもっとも」と、他人事のように受け止めているので腹も立ちません。私の手料理を入さまにお出しすることになったのも、それに値段がついたのも、すべて外からの働きかけのもと自然に始まったことで、 ことのなりゆきにいちばん驚いているのは、 この私なのですから。
ふるさとの木曾川を素っ裸で泳いで渡り切り、まわりのものを心配させ、あきれかえらせていたやんちゃな子供時代、私はいったいどんな未来を思い描いていたのでしょう。少なくとも、「精進料理の明道尼」と呼ばれるような人生を想像しなかったことだけはたしかです。
そもそも、しきたりや格式のようなものとは一切無縁、裸足で野山を駆けまわり、腰巻もせずに木に登り、ありとあらゆるいたずらをしでかし、お転婆を通り越して「あの子はアレを落として生まれてきた男の子にちがいない」と言われるほどに規格はずれだった女の子が、伝統の町・京都の寺に入り、「慎み深い女人」の代名詞のような尼になろうとしたというのがミステリーの始まりです。(規格はずれの女の子はしかし、どれだけ厳しい寺に入れられようと、どれだけ鋳型にはめられようと、ついぞ規格品になることができず、型破りの尼さんとして終わろうとしています)
自分の意志で「寺へ行く」と決めたことは覚えていても、たったの9歳で何を思ったというのでしょう。その心理もミステリーならば、大きくはみだしながらも尼僧であり続けたこともまたミステリー。尼僧としてあるべき姿と天然の私との間の相剋が限界まで深まるたびに、不思議と誰かと出会い、大きな事件と出くわし、ふと気がつくと行き止まりに見えた道の脇に、規格はずれのままでもどうにか歩けそうな新しい小道があらわれ、また一歩を踏み出さざるを得なくなるのです。どの出会い、どの事件が欠けても今の私はないことを思えば、こんな私を尼僧のままで生かそうとする目に見えない力が働いていることを意識せずにはいられません。そうだとしたら、いったいそれはどんな力なのでしょう。そしてなぜ?
思えば私の人生は「なぜ?」の連続です。その最たるものが恋をしたこと。女性であることをすっかり忘れて生きてきたようなこの私が、なぜ33歳にして初めて、なぜ25歳も年上のその人を好きになったのか、自分でも不思議でなりません。そして、尼僧でありながらひとりの男性に焦がれ、心をすっかり囚われてしまった私は、まるでその報いを受けるかのように交通事故に遭い、右手と右脚の自由を失うのです。
恋は恋、事故は事故。すべてが偶然と言ってしまえばそうかもしれません。おもしろいのは、ひとつひとつは偶然にすぎなくても、偶然が意味ありげに積み重なれば、ミステリアスな必然のように見えてくるということです。不思議なことに、私の人生は事故でいったんリセットされたあと、以前にも増して、いやそれ以上に豊かな展開を見せ始めます。
「なぜ?」この答えを知りたいと思う心は、人生最大の悲劇ともなりえた大怪我さえ、 ここへ辿りつくために必要な道程だったと素直に得心させてしまう力があります。しかし、いくら考えても正解というものがあるわけではなく、ああだったのか、いや、こうだったのかと思い巡らしては、一度出した答えを(なかば楽しみのようにして)頭の中で何度も書き直しているので、私は退屈ということを知りません。ひとつたしかなことは、あの事故がなければ、今、生かされて、ここにあることの歓びを、真に理解することは難しかっただろうということです。
付録の人生
昭和38年7月20日。朝から忙しい日でした。急用を思い出し、着物の被で額の汗をぬぐいながら月心寺の通用門を走り出た私は、国道一号線を逢坂出の坂道から舗道めがけて暴走してきた自動車に跳ね飛ばされました。二軒の家の軒をめちゃめちゃにするほどの大事故だったというのに、私が覚えているのは体がふわりと浮き上がったときのえもいわれぬ気持ちょさだけで、次に気づいたときはベッドの上。
右腕と右脚の骨が微塵に砕け、大量の血と泥にまみれた私は、近くの診療所にかつぎこまれ、 ハサミで着物を切り裂いて裸にされたあと、まるで俎板の上に載せられた巨大な鰤か何かのようにホースで水をかけられ、たわしでゴシゴシと洗われたそうです。見ている人が気を失うほどの壮絶な処置にも本人は気づかず、三日間、生死の境をさまよいました。
意識を取り戻した私の第一声は「おしっこしたいッ」だったそうです。「おお、ものを言いおった、もう大丈夫や。したければ、せい」。そう言われても「でえへん」と戸惑う私に、「野原でしたことあるか」とその声は訊いてきます。修行で托鉢に出ていた頃のことを思い出してうなずくと、「野原だと思ってせい」。それが元軍医の岡本診療所長との最初の会話で、こわもてのようで実はとてもおもしろい先生でした。
「ここ、野原じゃないみたいや。なんで私寝てんの?」「自動車に探かれたんや」「誰が?」「あんたが」と、漫才のような会話は続きます。「轢いた人は?」と私、「何ともない」と先生。そのあと私は「それはよかったですなあ」と言ったらしく、その悠揚たる態度が死にかけた女にはあまりに不釣合いだったので、頭のほうは大丈夫なのかと先生は不安に思ったそうです。
一命をとりとめた私は診療所から高折病院に移され、月心寺の責任役員でいらした高折隆一院長の特診患者として、可能な限りの治療を施していただくことになりました。命を救ってくださった岡本軍医、動けるようにしてくださった高折院長、院長先生の助手として手術に立ち会い、院長先生亡きあと主治医を務めてくださっている原田稔先生(現・原田病院院長)――
私はなんと医者運に恵まれたことでしょう。医師として優れているだけでなく、人間としての魅力にあふれた素晴らしい方たち。月心寺に来ていなければ、事故にも遭わなかったかゎりに、その方たちとの出会いもありませんでした。
息を吹き返してからの私は、少しでも動くと体じゅうの骨がガタガタに砕かれるような激痛に襲われるので、身じろぎひとつできません。体に載せる一枚の布切れの重さすら耐えられないので、真っ裸に近い格好で寝かされ、トイレも食事も仰向けのまま。生きるために必要な行為のすべてを人に依存し、自分ひとりでできることといえば、ただ息をすることだけでした。
そんな私にも、すべての人と同じように容赦なく時が流れていきます。気がつけば半月ほど過ぎ、お盆の時期に入っていました。僧侶でありながらお盆のお勤めも果たせず、苦痛と戦いながら終日天丼を見つめているだけの私――
。
「先生、いつになったら歩けるやろ?」ある日、私は訊ねていました。
「一年はかかるな」と、院長先生。
「一年かかっても歩けなんだらどうしましょう」
「歩けるまで入ってるさ」
「歩けるまで入ってたらだんだん歳いきます」
畳み掛けるように問いを発する私の目を、院長先生がやさしく見つめています。
「あのな、赤ん坊、知ってるやろ。生まれたときは泣くだけが仕事。ただお乳飲むだけが仕事。垂れっぱなしや。あんた自分でええ大人や思うてるから不安にも思うかしれんが、実際、今のあんたは大きな赤ん坊や。でも赤ん坊はな、一年経ったら這い出しよんねやぞ。半年たったらつかまり立ちしてな、二年も経ったら障子全部破って伝い歩いて、そのうち自分ひとりで大きゅうなったような顔して親の言うことは聞かんと、やれ、やりたいことができた、やれ、ええ人ができたと飛んでいきよる」
「私もこの足で飛んでいけるようになるでしょうか」
「ああ、いける」
「こけて骨が折れたらどうしましょう」
「また来たらええがな。そのために病院がある。あわてなさんな。一年二年寝とっても、歩けるようになったらすぐ取り一尿せるのやから。お盆にお参りせんから罰が当たる?仏さまはそんな気の短い方じゃない。仏さまがあんたを生かしておきたくなかったら、すぐに死んでるはずやから。あんたが生きてるいうことはな、あんたが必要だから生きてんのや」
そんなことがあってから、生きている者の事情でお盆の行事をとりやめたり、仏事を省略したりすることに、ちっとも抵抗を感じなくなりました。それよりも、私を助けてくださった方たちに顔向けのできないような生き方だけはすまい、と思う心がしきりに働きます。いちばん大事なことは、自分を偽らないこと。そして、真実を語ること。それに伴うリスクなど、一度死んだと思えばどうということもぁりません。
そう、私は39歳で一度死んだのです。あのとき生き返らなかったら、すべてがそこで終わっていた。39歳からの人生は、だから私にとって、付録のような、おまけのような、思いがけない天からの贈り物。ありのままに生きなければ、それこそ罰があたりましょう。
村瀬明道尼 むらせみょうどうに
大正13年(1924)年、愛知県に9人兄弟の5五番目として生まれる。9歳で京都の高源寺の養女となり、仏門に入る。岐阜県岐阜市の天衣寺・美濃尼衆学林での修行後、京都府八幡市の水月寺の副住職、福井県高浜市海見寺の正住職を経て、滋賀県大津市の月心寺へ。39歳のとき交通事故で瀕死の重傷を負い、右手・右足の自由を失う。その後、会席の精進料理が評判となり、料理の世界へ。特にごま豆腐は「天下一」と賞され、「精進料理の明道尼」として知られることになった。平成13年放送のNHK朝の連続テレビ小説「ほんまもん」では料理人を目指す主人公の師匠「庵主さま」のモデルに。著書に「月心寺での料理」(文化出版局)、「ある小さな禅寺の心満ちる料理のはなし」青春出版社)
がある。月心寺:滋賀県大津市大谷町27‐9 |